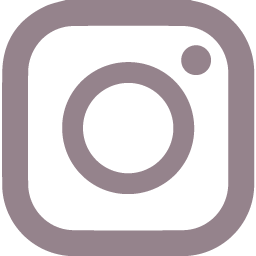鍋島焼の誕生
肥前(佐賀県)を領有していた大名鍋島直茂は、文禄・慶長の役に際し朝鮮へ渡った帰国の時、産業振興をねらって陶工を召聘して唐津焼きの興隆を促進させました。直茂の後を継いだ佐賀藩主勝茂は、日本人にとって念願であった磁器原料が領内で発見されたことを聞いた時は、きっと快哉を叫んだことでしょう。
白磁鉱石は、1605年(慶長10)頃に佐賀県西部、有田町の東のはずれにある泉山という小さな山から発見されました。発見したのは朝鮮から渡来した李三平という陶工です。当時日本で人気のあった中国の景徳鎮窯の染付を手本にしてスタートした伊万里焼は、大量に輸入されていた景徳鎮窯の染付磁器と競合する羽目となりました。鍋島藩は、日本の誇る伊万里焼の技術をもって、特別な献上品をつくる藩窯を築くことを画策しました。1628年(寛永5)年頃、有田と不離不即の関係を保つため、あえて人里離れた隣の伊万里市の山間の地、大川内に窯が築かれました。伊万里焼の最先端の技術を駆使し華美を避け優美典雅でありながら、いずれの国にも負けない独創的な様式の確立を目指したのが鍋島藩窯でつくられた鍋島焼です。制作は皿が中心で一尺、七寸、五寸、三寸の円形に定められ、厳選した素材を使い、オリジナルのデザインが起こされ献上品としての格式の高さが表現されました。その最盛期は元禄年間(1688~1704)です。


鍋島藩と今泉今右衛門
鍋島藩は、精妙無比で高度な日本の色絵磁器を作るため色絵付は有田赤絵町の赤絵屋に委託しました。なかでも技術の優れた今泉家は御用赤絵屋として代々藩窯の色絵付を行いました。厳正に検品された赤絵素地は藩吏の付添人の下に赤絵町の今泉家に托送されました。今泉家では斎戒沐浴して色絵付し、赤絵窯のまわりには鍋島藩の紋章入りの幔幕を張りめぐらし、藩吏の監督と警固の下で赤絵窯を焚き続けたと伝えられています。古文書には、赤絵町の赤絵屋衆が今右衛門家の技術の優秀さを「本朝無類」の色絵と認めていることが書き記されています。

明治になり鍋島藩の廃藩とともに御用赤絵屋制度がなくなったため、十代今右衛門は1873年(明治6)、絵付けのみではなく素地から制作するために本窯を築きました。窯焼きの経験が少ないため当初は失敗の連続でした。金銭的に困窮を強いられましたが、十代は積極的に新しい技術を取り入れるなどし、鍋島の伝統を受け継いだ色鍋島や古伊万里の逸品の再興に挑みました。制作された品の多くは食器ですが、精密な絵付けの秀作で、有田で最高水準の窯芸技術を追求した作品ばかりです。

十代につづき苦境の時代に苦労を重ねたのが十一代です。1927年(昭和2)に襲名した十一代は、世界恐慌(1929)や第二次世界大戦(1939)により販路を失いましたが、このような世情の中でも十一代は作品の質の向上につとめ、昭和の新しい時代にマッチする古典と近代を融合させた新様式の制作を模索しました。達者な画工でもあった十一代のレベルの高い絵付けを施した作品が認められ、宮内庁、各宮家の御用達をうけるまでとなりました。逆境に耐え打ち勝つために闘志をより強いものとしたからこそ十一代は傑出した作品を生み出すことができたのです。

十代、十一代に教えを受けた十二代は敗戦の混乱の中、1948年(昭和23)に襲名しました。4年後には、無形文化財に指定されるなどようやく今泉今右衛門の地位を名実とも確立することができました。昭和30年代に入ると十二代は創作的で革新的な意匠の制作に力を入れるようになります。先代の作品から一歩踏み出した新しい意匠は、和洋問わず近代化する建築様式にあった色鍋島として広く注目を集めました。

東京美術学校を卒業した十三代は、吹墨、薄墨、吹き重ねといった技法の考案、そして伝統的な図案に自らの写生から得た図案を融合させるなど、これまでにはない現代的な感覚で鍋島を再現した独自のスタイルつくり上げました。十三代は300年の伝統を誇る色鍋島に新たな世界を打ち立て、また日本の工芸界にも多大な影響を与えた傑出した陶芸作家です。こうした先代たちの心を受け継いだ十四代もまた、自らの新しい創意を吹き込んだ作品を制作し、今右衛門窯の歴史に新たなページを刻もうとしています。